雪の正月を飾る紅白の餅の花

冬の飛騨高山は、凛として美しい。雪の中で見る古い商家の格子や柱は
しっとりと雪黒く塗れまるで黒絵を思わせる情景だ。だが、暮れも近づく頃になると、
モノトーンの世界に色を添える華やかな花餅が出回る。
「寒さの厳しい飛騨では、冬は花が少なくなります。そのため、
餅を小さく切って木の枝に巻き付け、花に見立てて飾っていたんです」
由来を説明してくれたのは、小屋垣内 秀之(こやがいと)さん(63歳)。
今では、東京からも注文がくるほどで、毎年12月24日からは一家あげて
花餅作りに追われるという。小屋垣内さんは飲食店や旅館・ホテルなどに
納める。大きな花餅を手がけることも多い。人の背丈ほどあるものは
出来上がるまでに、大人4人がかりで約3時間かかる。紅白の餅を等間隔に、
乾いてもずれないように、しっかりと枝に巻きつけるのがコツだ。
しかし、あくまでも花のつぼみのようなふっくらとした感じを残して
おかなければならない。
花餅は明治時代には、枝に餅を丸めて付けた繭玉のような形で、壁に掛ける
スタイルだった今のように切り株の置物になったのは、戦後のことだったという。
かつては冬の間中、床の間に飾っておき雛祭りには枝から餅をはずし、アラレにしたそうだ。
小屋垣内さん、頼まれて花餅を作るようになってから33−34年経つ。
毎年11月中頃になると、土台となる切り株を探しに行く。適材は通称カスグスギ
(ネジキ)と呼ばれる広葉樹。丈夫で、枝も折れにくい。
「うちは自然の形そのままの株を使うので、水を張った水盤に浸しておくと
春には新芽が出ます。秋になると、紅葉も楽しめるんですよ」最近は、
なかなか形のよい切り株が見つからないのが悩みだ。
朝市に花餅が並ぶ頃は、正月支度に忙しい。
新春を迎えるとはいうものの、雪の季節もこれからである。
 家族総出で、天井にも届きそうな枝に餅を付ける小屋垣内さん一家。毎年40株弱の注文を受け付けるという
家族総出で、天井にも届きそうな枝に餅を付ける小屋垣内さん一家。毎年40株弱の注文を受け付けるという
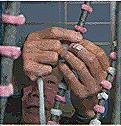 棒状に細く切った餅を、しっかりと枝に留めるにも熟練の技が。紅白の餅の花は梅の蕾のようにかわいい
棒状に細く切った餅を、しっかりと枝に留めるにも熟練の技が。紅白の餅の花は梅の蕾のようにかわいい
 華やかさには欠けるが、上品な昔ながらの白一色の花餅。明治の民家として国の重要文化財に指定された日下部民芸館で。
華やかさには欠けるが、上品な昔ながらの白一色の花餅。明治の民家として国の重要文化財に指定された日下部民芸館で。
 暮れが近づくと、朝市にもしめ縄や正月飾りとともに花餅も並ぶ。最近は、観光客の土産として人気が高い
暮れが近づくと、朝市にもしめ縄や正月飾りとともに花餅も並ぶ。最近は、観光客の土産として人気が高い
なを、このページは小学館発行”サライ”12/18号特集餅を極めるより写しました


 家族総出で、天井にも届きそうな枝に餅を付ける小屋垣内さん一家。毎年40株弱の注文を受け付けるという
家族総出で、天井にも届きそうな枝に餅を付ける小屋垣内さん一家。毎年40株弱の注文を受け付けるという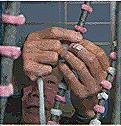 棒状に細く切った餅を、しっかりと枝に留めるにも熟練の技が。紅白の餅の花は梅の蕾のようにかわいい
棒状に細く切った餅を、しっかりと枝に留めるにも熟練の技が。紅白の餅の花は梅の蕾のようにかわいい 華やかさには欠けるが、上品な昔ながらの白一色の花餅。明治の民家として国の重要文化財に指定された日下部民芸館で。
華やかさには欠けるが、上品な昔ながらの白一色の花餅。明治の民家として国の重要文化財に指定された日下部民芸館で。 暮れが近づくと、朝市にもしめ縄や正月飾りとともに花餅も並ぶ。最近は、観光客の土産として人気が高い
暮れが近づくと、朝市にもしめ縄や正月飾りとともに花餅も並ぶ。最近は、観光客の土産として人気が高い